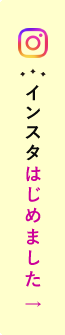保育の特徴
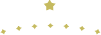
キリスト教について
一人ひとりを大切にし、
神と人から
愛されている喜びを伝える
教育を目指しています。

聖クリストファ幼稚園は1956年アメリカ人の
シスターマリヤ・マーガレットを初代園長とし、
「幼子をキリストへ」の思いを持って幼児教育を
スタートいたしました。
幼稚園の名前の由来
今から半世紀以上前、園舎が立つ予定だった地は、たいへんなぬかるみだったそうです。
そこで思い浮かんだのが、「川を渡る旅人を救われた聖人(神さまを担いで川を渡った聖人)・聖クリストファ」の名前だったそうです。
本園の教育の柱はキリスト教です。
一人ひとりを見つめ、尊敬・尊重し、抱きしめる・・・そんなあたたかで丁寧な保育、命と人格を大切にする保育を目指しています。
一人ひとりを大切にする・・・それは何も大げさなことではなく、何気ない毎日の生活の中で、ほんの少し心を配ることから始まると思います。
たとえば朝、子どもたちを迎えるときに「おはよう」と言うだけでなく「○○ちゃん、おはようございます」ときちんと一人ひとりの名前を呼び、立ち止まって笑顔で挨拶をすること。お部屋の中に、いつも小さなお花を飾ること。

お休みしたお友達のために「△△ちゃんのお病気が早く良くなりますように」とみんなでお祈りすること。
すれ違ったりお話しするときに笑顔をかわしたり、手をつないだり、そっとなでたりする…
子どもたちが「自分は愛されている」という喜び感じることができるよう、思い・言葉・仕草・まなざし・ふれあい・心づかい、様々な形で伝えたいと思っています。 そして卒園してもなお、うれしいとき、悲しいとき、どんなときでもここに帰って来られるように、両手を広げて待っていたいと思っています。

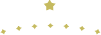
モンテッソーリ教育について
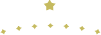
モンテッソーリ教育に
基づいた生活
本園では集中力、持つ力、選ぶ力、考える力、そして何より、「他者への配慮の心」が自然に育つような生活を送っています。
モンテッソーリ教育は、イタリアの医学博士でキリスト教信者でもあるマリヤ・モンテッソーリ女史による教育法です。
3歳から6歳までの吸収力のすぐれた大切な時期に、子供たちのために環境を整え、その中で一人ひとりが自分でやりたいことを見つけて取り組む「おしごと」と呼ばれる自主選択活動が特長です。

「おしごと」とは、やってみたい活動を自分で選び、指先や五感を使ってよく考えながら、じっくりと取り組む楽しいひと時です。
活動を終えた後は、「やった!できた!」という達成感・充実感を感じたり、「もっとやってみよう!」という意欲が生まれます。
「ひとりでできた!」という体験を重ねることによって自信や自立心が芽生え、自分自身を愛し大切に思う気持ちが育ちます。
自分のことが一人でできるようになったり、満足感を味わった子どもたちは、周りを見渡すゆとりが出てくるので、誰かが困っていることに気づいて寄り添ったり、そっと手助けをするなど、人に親切にする気持ちや、自分と同じように人を愛し大切に思う気持ちが自然に育っていくのです。

教師は子どもがやってみたいと思っていること、難しくて困っているところを受け止めて、一人ひとりにそっと寄り添い関わります。
「こうやってするのよ。よく見ていてね。」と、子どもがよくわかるように一つ一つの動きをゆっくりと「やってみせる」ことで示します。
一人ひとりに寄り添って教える…それはまるでお母さんが赤ちゃんにミルクをあげるときのような、ゆったりとした、愛情たっぷりのひと時です。